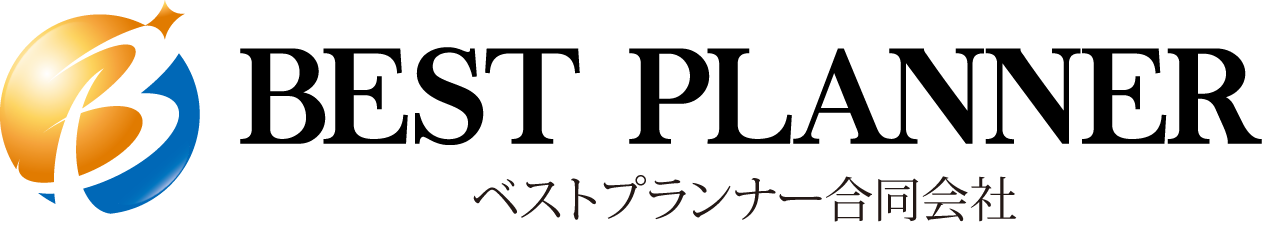ICT環境
テレワークが急速に広まった理由の一つに、情報技術の進歩が挙げられます。
数年前までのテレビ会議システムは、頻繁に音声が途切れたり、映像がスムーズに動かないことも珍しくありませんでした。そのような環境では満足な会議ができず、メールやチャットなどの文字情報に頼らざるを得ませんでした。
しかし、情報技術が進歩した今、高性能なテレビ会議システムにより、映像や音声を使ったコミュニケーションが身近なものとなっています。
このように、技術の飛躍的な進歩にによって、テレワークは格段に実施しやすくなっているのです。
テレワークを実施するにあたり、職場にICTを整備するだけでなく、テレワークで働くスタッフの自宅の作業環境やオフィス環境も見直す必要があることを忘れないでください。
必要なITツール
テレワークに必要なハードウェアといえば、パソコンが不可欠です。用意したパソコンには、業務やコミュニケーションに必要なソフトウェアをインストールしておきます。他に、テレビ会議を行うためのカメラとマイクも必要です。
モバイルワークを行う場合は、インターネットに接続できるスマートフォンまたはタブレットがあると便利です。
次にソフトウェアです。普段オフィスで使用している業務ソフトウェアのほかにも、業務を補助するITツールを準備します。インターネットを使ってリアルタイムにコミュニケーションが取れるチャットシステム、映像や音声のやり取りができるテレビ会議システム、スケジュールや資料を共有えきるグループウェアがあるといいでしょう。
デバイス
テレワークに必要なデバイスは企業が支給するのか、悩む企業も少なくないようです。
社員の私物をテレワークで使用すると、テレワーク導入時の費用が抑えることができます。しかし、個人のデバイス上で何かトラブルが発生した場合、問題を解決するために個別に対処しなくてはなりません。また、私物のパソコンがウイルスに感染していることに気づかず、そのまま業務システムにアクセスしてしまうと企業内のICT環境にウイルスが侵入するリスクが高まります。
コストやセキュリティ、トラブルの発生などを総合的に判断すると、テレワークで使用するデバイスは企業から支給する方が望ましいと考えられます。その際には、セキュリティシステムや必要なソフトウェアを搭載できる十分な性能を持ったデバイスを用意する必要があります。
ネットワーク
自宅においてテレワークで働く人の多くは、自宅のインターネット回線を使用しています。それに加えて、デザリングができる機器、もしくはモバイルWi-Fiを用意すると便利です。
デザリングとは、モバイルデータ通信ができるスマートフォンやタブレットに接続することで、パソコンでインターネットを利用することができます。また、モバイルWi-Fiとは、持ち運びができるWi-Fi接続のための端末のことを言います。
テザリングやモバイルWi-Fiは、場所を選ばずインターネットに接続することができるので便利に使用できますが、通常の業務に支障がない通信容量を備えておく必要があります。
モバイルワークの際に企業が支給したスマートフォンを使用する場合には、スマートフォンのみでパソコンのインターネット接続まで行えるテザリングをおすすめします。テザリングなら、電話もインターネット接続も端末一つで行うことができます。
ソフトウェア
テレワークを滞りなく行うためには、オフィスで使用している業務用ソフトウェアの他に、遠隔業務の補助をするソフトウェアが必要になります。
以下のようなコミュケーションツールや情報共有のためのツールを使うことによって必要な情報をオンライン上で共有し、テレワークでもスピーディーに業務を遂行することができます。
チャットシステム
チャトシステムとは、複数のメンバー同士が文字によるやり取りをする「チャット」を行うためのツールです。チャットはリアルタイムでコミュニケーションが取れることが特徴で、生産性の向上にも役に立つツールです。
ビジネス用に開発されたチャットシステムは、個人用チャットシステムよりもセキュリティレベルが高く、アカウント管理もできるようになっているのでお勧めです。
テレビ会議システム
テレビ会議システムとは、映像と音声、資料のやり取りによってオンライン上で会議を実現します。
テレビ会議システムを使えば、テレワークでも社内コミュニケーションが維持できるほか、他社との打ち合わせに使用すれば、移動時間や交通費の削減にもなります。
グループウェア
グループウェアは遠隔で業務行っていても、オフィスにいるかのように業務を行える場を整備するシステムです。
グループウェアには、スケジュールやタイムカードによる在籍情報の管理、仕事に必要なファイルや掲示板の情報公開と管理、報告書や社内メール、メッセージのやり取りなどが可能です。
同期型と非同期型
同期とは、データの送信側と受信側で処理のタイミングが一致していることを指します。一方で非同期は、送信側と受信側で処理のタイミングが一致していないことを意味します。
コミュニケーションにおける同期とは、リアルタイムで双方のやり取りが可能なこと。対面での会話や電話、テレビ会議システムがこれにあたります。
コミュニケーションにおける非同期とは、各々が自分のペースで一方向に情報交換し、やり取りを成立させること。チャットやグループウェア、メールがこれにあたります。
運用形態
ソフトウェアの運営形態には、オンプレミスとクラウドがあります。
オンプレミスは、従来一般的だった運用形態で、使用者が管理する設備内にサーバーを設置して、ソフトウェアをインストールして利用します。
一方、クラウドは新たに普及してきた形態で、インターネットなどのネットワークを経由してソフトウェアサービスが提供されます。クラウドサービスは、提供元のサーバーに接続することでソフトウェアを利用するため、インターネット環境が整っていれば、利用者側の設備内にサーバーを設置する必要はありません。
クラウドは、インターネット環境さえあれば社外からのアクセスが簡単にできるため、自宅でのテレワークや出先でも使いやすいと考えられています。また、サービスを提供している事業者によってメンテナンスが行われるので、常に最新版のソフトウェアを使うことができます。
作業環境
テレワークを始めるには、使用する端末やインターネット環境だけでなく、作業環境を見直す必要があります。
長時間にわたって作業することを考え、それに適したデスクや椅子、照明についてもオフィス同様に自宅などの作業スペースに整備しなくてはなりません。もし、作業環境として適さない場所で長時間作業を連日行うと、テレワークで働く人の健康を害する恐れがありますし、生産性が下がることも考えられます。
長時間作業をしても健康を害さず、集中力を保って仕事ができる環境づくりが求められます。
厚生労働省が公開している、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」・「自宅等でテレワークでを行う際の作業環境整備のポイント」を参考にするとよいでしょう。
環境整備の費用
テレワークに必要なデバイス、ネット環億環境、作業環境と、企業が用意すると思われる設備について説明をしました。これらを一度に整備するとなると、費用負担が大きくなります。
実際にテレワークで働く社員の困っていることなどを情報収集し、実状にあった環境整備の援助を行うとよいでしょう。テレワークの浸透に伴い負担の幅を徐々に広げていくのも一つの方法です。
テレワークを行うと、通勤や移動にかかる費用が削減されるので、その浮いたコストを環境整備に充てることもできます。また、国の助成や補助を受ける方法もあります。
視点を変えて、テレワーク導入のための費用をコストではなく投資と捉えてはいかがでしょう。
テレワークを定着させることができれば、BCP対策や業務効率化ができ、優れた人事戦略にもつながります。このように企業にもたらす効果を考えれば、環境整備にかかる費用は投資といえるのではないでしょうか。
オフィス環境
社内でテレワークが浸透すると、オフィスの使われ方も変わってきます。
オフィスワークとテレワークを併用するのであれば、オフィスで働く人がテレワークで働く人と会議を行うこともあります。そんなときは、オフィスにいてもテレワークと同じようにテレビ会議に参加するための場所が必要になります。自席でテレビ会議をすると周囲の妨げになることもあるので、専用スペースがあると便利です。
次に、テレワークによっておこるオフィス変化は、ペーパーレス化です。
テレワークを導入すると、必要な情報はオンラインで共有されるため、紙の書類が圧倒的に減少するでしょう。紙の書類が減少すれば、資料や資材の量も減り、その保管場所の面積も圧縮されます。
ペーパーレス化で書類の保管場所が減る一方で、テレワーク用のディスプレイやテレビ会議用のヘッドセットなど増えるものもあるでしょう。
テレワークを始めると、オンライン上のシステムだけでなく、物理的なオフィス環境も変化しますので、テレワーク導入時には、オフィスの見直しも忘れないようにしましょう。
セキュリティ
新しいITC環境や設備を導入すると、情報漏洩のリスクが上がるのではという不安を抱える企業が少なくありません。
今まで職場内で管理されていた書類や電子データの情報が、テレワークになるとインターネット上でやり取りされることに不安を抱くかもしれません。確かに、業務用デバイスのウイルス感染や社内システムへの不正アクセスなどのリスクはあり得ます。このようなリスクに対しては、システム管理者による技術的な対策が必要になります。
テレワークで働く人のセキュリティ意識
テレワークでは、自宅以外に移動中の電車の中やカフェなど、社員以外の人が立ち入る場所で作業することがあるかもしれません。また、デバイスとともに社内情報を社外に持ち出されることにもなります。
技術的なセキュリティ対策をしても、日常的なミスやトラブルで情報漏洩が起こるリスクもあります。
例えば、「電車内でパソコンを開いていて、隣の人に画面をのぞき見された。」「スマートフォンを置き忘れて紛失した」「外出先でオンライン会議をしていたら、周囲に内容が聞こえていた」などです。
テレワークで起こる情報漏洩のリスクは、日常の不注意に潜んでいることが多いのです。
実際に業務内で情報を扱う社員や責任者は、日常的なミスから情報漏洩を起こさないよう十分気を付けなくてはなりません。また、このようなミスを完全に防ぐことは難しいと認めなければいけません。
万が一、このような事態が起こってしまったとき、迅速に対処できるよう準備しておくことでリスクを最小限に抑えることができます。
このようなリスクを最小限にするためには、情報の取り扱いに関するガイドラインを策定し、順守することが必要です。当たり前に思える内容でも、改めて文章で確認することで注意喚起になります。策定したガイドラインを全社員に周知して、各自のセキュリティ意識を高めるようにしましょう。
総務省が公開している「テレワークセキュリティガイドライン」を参考にするとよいでしょう。