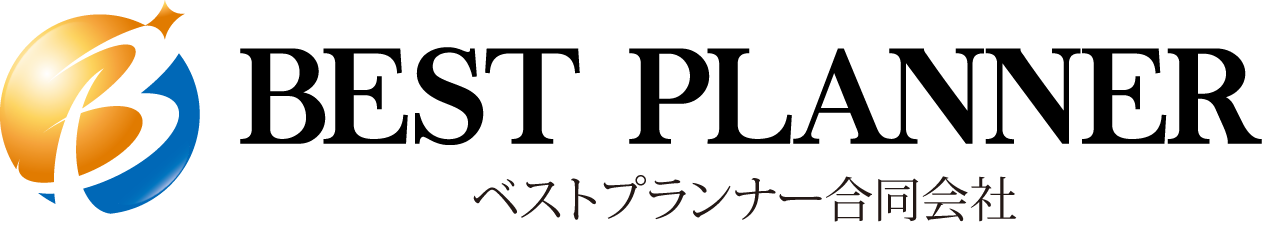良い改善策やアイデアを持っていても、それを実行し継続しなくては意味がありません。
しかし、業務改善を行った企業をみると、「馴染まない」「続かない」と元に戻っていることも少なくないようです。
改善策を定着させるにはどうすればよいのでしょうか。
仕組みづくり
面倒な仕事などは「わざわざ」しているという感覚があるのではないでしょうか?たいていの人は、「わざわざ」する作業を避けたがる傾向にあります。「わざわざ」ではなく「自然に」できれば継続につながるのではないでしょうか。
例えば、「既存の行動にプラスする。」無理のない変化は自然に対応することができます。ほかには、議事録を写真で残して共有するなどの「一部自動化。」大きく変えるのではなく、少し変えることで抵抗なく改善を続けていくことができます。
「わざわざ」している業務を見える化しましょう。「わざわざ」を減らすために「重要度が高いのにやらない、続かない」ものを浮き彫りにします。その「わざわざ」を「自然に」へ近づけるように変化させることがポイントです。
新しいことを始めようとすると「面倒だ」と抵抗を持つ人もいるので、「わざわざ」ではなく「自然に」できる仕組みを考えましょう。
強制としつこさ
「自然に」できることばかりではないので、ある程度の「強制」は必要になるでしょう。
人は、目の前にある仕事を優先させる傾向にあります。改善策などは、やればよい結果が得られると分かっていても、後回しになってしまうことが多々あります。個人の自主性に頼りすぎることなく、改善活動を牽引する人を置いたり、定期的に検討の場を設けるなど、改善活動が途絶えないようにある程度の「強制」をすることも大切です。
ホウレンソウ(報連相)
ホウレンソウ(報告・連絡・相談)は、誰もが最初に指導されるものであり、部下が上司にすることが常であると思います。しかし、業務改善する環境を組織全体に定着させるためには、上司から部下へのホウレンソウが大切なのです。
メンバーが考えた改善策やアイデアを上司が預かったなら、その後の進捗状況や検討状況をメンバーにフィードバックしましょう。預かったものを放置すると、メンバーのモチベーションも下がり、改善しようという気持ちまでも無くしてしまう恐れがあるのです。チームの信頼関係は上司の受け止め方次第で変わってしまいます。チーム内の定例会議などで、進捗を確認したりフィードバックすることで、改善の風土を作っていきましょう。
説得するのではなく納得してもらう
新しいことを始めようとすると、反対する人や無関心な人も少なからずいるかもしれません。
人は説得しようとすると抵抗してしまうものです。ですが、人は納得すると主体的に考えて動こうとするものです。
説得することも大事ですが、一歩引いて納得してもらうように考えてみましょう。
抵抗や無関心の裏にあるもの
反対する人にも理由があるはずです。どんなことが考えられるでしょうか。
新しいことを始める、やり方を変えるということは今までとは過程が違う、結果が変わってしまうかもという恐怖心を抱いてしまうもの。おそらく多くの人は、改善された後の状況を想像できないから不安を感じているのです。
改善後を想像できないと良いとも悪いとも言えず、変化に対する恐怖心の方が勝ってしまい、非協力的な態度をとってしまう場合も考えられます。改善した後の世界をイメージできるように、見えない敵を味方に変えるように、未知への恐怖心を取り除く努力をしましょう。
対立と結束
心理学者のタックマンが唱えた「タックマンモデル」という概念があります。
チームは様々な衝突や混乱を経て理想的に機能するものです。「タックマンモデル」とは、チームを立ち上げてから5つの成長段階を経て成果が出せる状態になることを示したフレームワークです。
- Froming(形成):メンバーはお互いのことを知らない。また共通の目的等も分からず模索している状態。
- Storming(混乱):目的、各自の役割と責任等について意見を発するようになり対立が生まれる。
- Norming(統一):行動規範が確立。他人の考え方を受容し、目的、役割期待等が一致しチーム内の関係性が安定する。
- Performing(機能):チームに結束力と一体感が生まれ、チームの力が目標達成に向けられる。
- Adjourning(散会):時間的な制約、事態の急変、目的の達成等の理由によりメンバー間の相互関係を終結させる。
意見の対立を避けて各メンバーが自由に意見を発している状態であれば、チームは統一されず、機能しません。対立は組織を健全に変化させるための要素の一つです。混乱期の対立を避けずにぶつかってこそ結束力が強くなるのです。
では、対立を健全な対立にし、発展的解消をするにはどうしたらいいか考えてみましょう。
- 意見を書き出す:お互いの意見を書き出し眺めることで冷静になり、共通点に気づくかもしれません。それによって発展的な解消方法を議論することができます。
- 第三者の参画:利害関係を持たない第3者にファシリテーター役として参加して牽引してもらうことにより、感情による水掛け論を防ぐ効果を期待します。
- 対立したままにしない:対立した後は、堅く握手できるような歩み寄りが大切です。お互いのリーダーが険悪の状態のままでいると、部下同士の仕事にも支障が出てしまうかもしれません。
健全な対立をする上で、目的意識と改善ストーリーが重要になります。なぜ改善が必要なのか。なぜ今までのやり方ではいけないのか。会社や組織のためになぜ必要なのか。それさえしっかりしていれば、対立の対立は生まれてこないでしょう。
伝え方を意識する
時と場合、相手との関係性にもよりますが、仕事をお願いするときに「指示モード」で伝えるか、「相談モード」で伝えるかによって、受け手の対応、気持ちは左右されます。
指示モードとは、「これ、お願いします。」「すぐ対応してください。」など一方的な依頼です。
相談モードとは、「上司から頼まれたんですが、お力を貸していただけませんか?」「今手が回らなくて。申し訳ないんですがお願いしてもいいですか?」などです。
指示モードでは受け手側がイラっとくることがあっても、相談モードでは「仕方ないな。手伝ってあげよう。」と思って動いてくれるかもしれません。
伝え方のトーンを切り替える、使い分けることは対立を生まないための工夫になります。
温度差のある改善は定着しない
社内や部内で働き方改革などのプロジェクトを立ち上げる時、有志を募ってチーム編成をする場合があります。そこに集まってきたのは意識の高い人たちが多いと考えられます。意識の高い人たち同士の議論というのは、その他の人、チームに参加しなかった人たちとの温度差が生まれてしまうものです。
意識の高いプロジェクトチームの人たちは、「選ばれしもの」というような感覚で連帯感とともに突き進み、やがて「なぜ、ほかの人にはわからないのか。レベルが低いのではないか。」と不信感を抱き、攻撃し始める。
反対に、プロジェクトに参加していない人たちは、「意識の高い人の集まりが、また突っ走っている。」と冷ややかな目で見ている。
このような状況になると、意識の高い人達が作ったレベルの高いソリューションは、現場で受け入れられにくくなり、組織に定着しにくくなります。もしくは、何とかスタートさせたとしても、道半ばで断念といった残念な結果になることが予想されます。
有志だけのプロジェクトチームは、立ち上がりが早いが現場との温度差が生まれ、空中分解する恐れがあります。
組織に定着させるには、プロジェクトチームのメンバーは選抜式にし、有志と選抜のハイブリットチームにするなど、バランスを考えたチーム編成がよいでしょう。また、プロジェクトチームが孤立しないように、定期的に上位者や現場との交流の場を設けるなど、組織内に温度差が生まれないように細心の注意が必要です。
広報戦略
改善や改革を定着させ、社内の協力を得やすくするためには、広報活動にかかってきます。社内の良い取り組みや地道な取り組みを社内報や社内イベントで取り上げてもらい、社員や関係者に周知してもらうことが効果的です。
プロジェクトメンバーの孤立を防ぎ、社内に一体感を
プロジェクトの狙いや活動の様子、メンバーの気づきなどを社内に周知することで、「改善や改革は一部の人間がやっている。何をやっているかわからない。」を無くし、社内の一体感を作り出せるでしょう。
しっかりとした広報活動をすることで、その改善や改革が会社にとって重要であることを社員全員に意識づけることができます。また、広報活動をすることによってメンバーにも光があたり、チーム全体のモチベーションアップにもつながります。
改革元だけではなく組織全体に
例えば、育児休暇制度。
制度導入をしたものの、制度利用者はごく一部の部門の人のみということがあります。せっかく導入した良い制度も社内全体で利用しなければ改革にはなりません。
そんな時こそ、広報を上手に使って情報発信してみましょう。
「生産部門の男性課長A氏が育児休暇を利用している様子を社内外に発信」
するとどうでしょう。会社が本気で働き方改革をしていることが社内外に伝わります。もちろん、社内の雰囲気も変化し、抵抗勢力も減少していくことでしょう。
働き方改革は人事戦略ではなく広報戦略。時には社長がトップダウンで改革の後押しのメッセージを発信したりするなど、広報を上手に利用して社内の改革への雰囲気を作るのもひとつです。
押し付けのやらされ感は何も生まない
ワクワク症候群
働き方改革→生産性向上→モチベーションアップ→ワクワクする職場
これは誰にでも当てはまるものでしょうか?
仕事の内容によっては、頑張ってもワクワクできないものもあります。また、ワクワクできない社員もいるでしょう。そんな人たちにワクワクを強制してもやらされ感しかありません。無理にワクワクを目指すのではなく、「悪くないかも」と思えるくらいを目指すのがいいのではないでしょうか。
- みんなが無駄だと思う仕事はやめる
- ネガティブ作業を無くす
- 部下の意見を上司がきちんと受け止める
- なんでも言い合える雰囲気を作る
このような取り組みを続けていくと、社員は「このチームなら頑張れるかな。「嫌なこともあるけど、仕方ないか」と思えるものです。そう、押し付けのワクワクは何も生まれてこないのです。
「らしさ」を大切に
どんなに素晴らしい改善手法も、その組織に合わなければ定着するはずがありません。最初だけは効果が出ることもありますが、結局定着せずに元に戻ってしまうことは少なからずあるようです。
頭では効果的だとわかっていることも、自分たちの風土に合わないやり方では、やらされ感だけしか生まれません。やらされ感はモチベーションも生産性も下げてしまいます。「らしさ」を無視して突き進んだ結果は、普遍化しつまらない職場になってしまします。そんなところから良い製品やサービスが生まれるでしょうか。
成功例をコピーして「らしさ」失ってしまっては、企業の存在価値を変えてしまいかねないのです。成功例を参考にし、自分たちの頭と心で考えることが大切です。変えてはいけないものは変えずに、無駄は減らす。そんな議論をして「らしさ」を大切にしましょう。