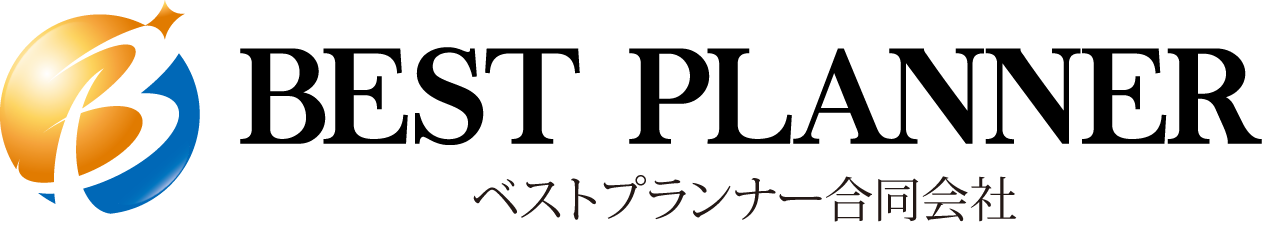在宅勤務は通勤時間が掛からず、育児や介護など家を空けられない都合があっても家で働くことができるなど、多くのメリットがあります。
しかし、その場にほかの従業員がいないため、どのように意思疎通を図ればよいか、という部分が課題になる場合もあります。
そこで、在宅勤務中にコミュニケーションを取るのに便利なツール8種類と、その特徴をご紹介します。比較して、最適なものを利用してみてはいかがでしょうか。
在宅勤務の課題はコミュニケーション
2020年3月、クラウドサービスpaperlogicを提供するペーパーロジック株式会社が、リモートワーク・テレワークをおこなう111人の会社員に実施した「リモートワーク・テレワーク」に関するアンケート結果を公表しました。
このうち「あなたの勤務先では、リモートワーク・テレワークの課題はどのようなものがあると感じていますか?」という質問に対し、「対面よりコミュニケーションが難しい」という回答が最多の45.9%でした。
相手がその場にいないということから、言葉が足りず勘違いをしてしまったり、直接話すよりも細かなニュアンスが伝わりにくかったりして、業務に支障が出てしまう可能性もあります。
そこで、チャットツールやオンラインミーティングなどのツールをうまく活用し、コミュニケーション不足にならないよう務めることが重要です。
在宅勤務におすすめのコミュニケーションツール
では、在宅勤務に便利なコミュニケーションツールを特徴とあわせてご紹介します。
Chatwork

その名の通りパソコンやスマホでチャットを利用できるビジネスツールです。タスクの作成や管理、ファイルのアップロード、ビデオ・音声通話なども利用することができます。
無料で利用することもできますが、有料プランに加入するとファイル添付可能な容量が増加、グループチャットの作成数などの制限が撤廃されます。
最上位プランの「エンタープライズ」であれば、社外ユーザーやIP・モバイル端末の制限などのセキュリティ機能が付加され、シングルサインオンなどより安全かつ便利に利用できます。
URL:https://go.chatwork.com/ja/
Slack

チャットやファイルアップロード、ビデオ・音声通話などの機能のほか、GoogleドライブやOffice365ほか2000以上のサービスとも連携させられるツールです。
また、ワークフローという機能では入社後の手続き、オンボーディングのフロー自動化、年末調整や健康診断など総務のオペレーションを効率化できるなど、優れた機能があります。
こちらも「エンタープライズ」プランを利用すれば、データ暗号化やアクセス状況の可視化など、セキュリティ性能をより高めることができます。
URL:https://slack.com/intl/ja-jp/
LINE WORKS

コミュニケーションツールとして知られるLINEは、ビジネス向けの「LINE WORKS」というサービスもあります。チャット画面は通常のLINEと同様のため、使い慣れた方はとくに利用しやすいことでしょう。
このほか、最大200人が参加できるビデオ・音声通話や、議事録・資料などを共有できるノート、ファイルアップロード、グループのメンバーが予定を共有できるカレンダーなどの機能があります。
また、トークBot APIを利用すれば、勤怠管理や業務報告、マニュアルの確認などをBot化し、ワンタップで簡単におこなえるようになります。
URL:https://line.worksmobile.com/jp/
Teams

チャット、ビデオ・音声通話やファイルアップロード、クラウドストレージなどビジネスに必要な機能が揃ったツールです。
Microsoftのサービスのため、OutlookやOneNoteなどと連携して利便性を高められるほか、Word/Excel/PowerPointといったOffice系ファイルにリアルタイムでアクセス、共有、編集もできます。
「Essentials」「Premium」などのプランではさらにExchange Online、SharePoint Onlineも利用でき、Slackと同様のワークフロー機能でフローの自動化、オペレーションの効率化が実現できます。
URL:https://products.office.com/ja-jp/microsoft-teams/group-chat-software
Zoom

ビデオ会議で知られるツールです。ビデオ・音声通話やオンラインミーティングのほか、チャットやファイル共有、Microsoft O365やGmail、Slackなどのアプリとの連携もおこなえます。
とくにオンラインミーティングはZoomのアプリをインストール、簡単なアカウント作成だけであとは招待されたURLにアクセスすればすぐに視聴できて便利です。
リモートコントロール機能もあるので相手に操作を伝えることができ、またホワイトボード機能ではスマホ・タブレットなら手書きで補足などができるなど、まるでその場で話しているように利用できます。
URL:https://zoom.us/jp-jp/meetings.html
Googleハングアウト

Google Chromeの拡張機能(アプリ)として利用できる、写真や絵文字、グループでのビデオ通話などの機能がある無料のコミュニケーションツールです。パソコン・スマホで利用できます。
無料のためGoogleアカウントがあればすぐに手軽にでき、ビデオ通話は1:1のほかに最大 10 人で通話できる「ビデオハングアウト」もあるので、少人数の会議に便利です。
履歴をオンにしておけば、ハングアウトでの会話履歴や共有した画像を一覧ですぐに確認できます。端末を切り替えてもそのまま表示できるため、電池切れなどの際もスムーズに会話を続けられます。
URL:https://chrome.google.com/webstore/detail/google-hangouts/nckgahadagoaajjgafhacjanaoiihapd?hl=ja
Skype

非常にポピュラーなチャット・ビデオ・音声通話ツールです。オンライン会議はサインアップやダウンロードも不要、クリック3回ですぐに会議をおこなえます。
通常のチャット、ビデオ通話は無料でも利用できますが、有料プランであればSkypeから固定電話への発信や、海外の相手とも格安で通話できる点が特徴です。
また、ビデオ通話では画面共有はもちろん、字幕付きでの会話もできるため、耳で聞き取りにくい場合も会話をスムーズにおこなえます。
Cisco Webex Meetings

世界最大のコンピュータネットワーク機器開発会社、Ciscoの提供するツールです。ビデオ会議およびオンラインミーティングでの利用に特化しています。
リンクのクリックだけで簡単に会議へ参加でき、会議の録画やブロードキャスト、画面やドキュメントなどの共有もおこなえます。
また、最大の特長は人数を気にせず誰でも招待できる点で、最大40,000 人以上の相手との会議も可能です。Office製品やGoogleのサービス、GitHubとの連携もスムーズです。
URL:https://www.webex.com/ja/video-conferencing.html
まとめ
このように、ビジネス向けのコミュニケーションツールは非常に充実しており、なかには無料で気軽に利用できるものもあります。
チャットやビデオ通話を使って、いつでも業務の報告・連絡・相談ができるような状態なら、会話不足でのミスなどを防ぐことができます。
会議をおこなう人数や利用したい機能をもとに、どのツールをメインで利用するか検討してみてください。